個人的に日本で一番好きな映画監督が、新作を撮ってついに帰ってきてくれました。
李相日監督の「怒り」以来6年ぶりとなる新作「流浪の月」がやっと公開です。次はいつ撮ってくれるのかと待ちわびていたので、本当に観れて嬉しいです!
そして6年待った甲斐があった!最高に切ない愛の物語を堪能することができました。邦画でここまで濃厚な映画体験と胸に突き刺さる感動がある作品は久々でした。
幸福、切なさ、苦しい、痛い、助けて、救い、劇中様々な感情に襲われて、深い感動が押し寄せてきました。
鑑賞から2日たった今でも、主人公二人の愛の行方と、お互いの優しい眼差しに想いを馳せずにはいられません。
さて、何がそこまで素晴らしかったのか、「流浪の月」の感想を書いていきたいと思います。
あらすじ
家に帰れない事情を抱えた少女・更紗(さらさ)と、彼女を家に招き入れた孤独な大学生・文(ふみ)。居場所を見つけた幸せを噛みしめたその夏の終わり、文は「誘拐犯」、更紗は「被害女児」となった。
15年後。偶然の再会を遂げたふたり。それぞれの隣には現在の恋人、亮と谷がいた。
(HPより抜粋)
以下、ネタバレ含みます。
(1)松坂桃李、広瀬すずの円熟した驚異の演技力。そしてホン・ギョンピョの映像美に圧倒される
今回は、ストーリーや演出に触れる前に、キャストの演技やカメラについての感想を最初に書いていきたいと思います。
まず、なんといっても主演の松坂桃李・広瀬すずの演技が素晴らしかったです。
松坂桃李は近年「孤狼の血」や「空白」「娼年」といった難役に挑戦し続け、確実に役者としての腕を磨き続けていた印象があります。著名で厳しい映画作家とタッグを組むことで役者としての幅がどんどん進化しているイメージです。
その役者としての実力が、本作でも安定感のある深みに繋がっていたと思います。基本的に一切感情を表さず、何を考えているのか、なぜ誘拐したのか、その意図が全く掴めないという難しい役どころでしたが、感情を顕にする瞬間もあり、その微妙な表情のニュアンスで文というキャラクターを表現していて、素晴らしかったです。そして何より文を表現するためにガリガリに減量し、顔つき体つきが普段の松坂桃李からかけ離れた、文そのものになっていることにも驚きました。
広瀬すずも、李相日監督とは「怒り」以来二度目のタッグ。「怒り」でも米兵にレイプされる少女という難役をこなし、当時キラキラ高校生の役のイメージが強かったので、観た時にかなりの衝撃を受けたことを覚えています。
そこで李監督に見込まれて今回の主演に繋がったのだと思いますが、李監督の期待通りの表現を見せてくれたのではないかと思います。更紗と文だけにしか分からない絶妙な空気感や、恋人である亮との確執を静かながら表現されていたと思います。
キャストでもう一人衝撃だったのは、更紗の子供時代を演じた白鳥玉季です。
若干12歳にして、大人の色気と表情、そして正反対の子供らしい表情。その二面性を表しており、大人顔負けの演技をこなしていたと思います。12歳でこの存在感、末恐ろしいですね・・・
横浜流星も今までの清純なイメージとは打って変わって更紗を苦しめるDV彼氏として十分な存在感を発揮していました。新境地開拓で、今後の横浜流星も注目していきたいです。
そして「流浪の月」では撮影監督に「パラサイト」を撮ったホン・ギョンピョが参加しています。全編を通して映し出される映像は非常に美しくて、ため息が出るようなショットもいくつか存在しました。
この物語が持つ神秘的な寓話性を、ホン・ギョンピョが作り出す映像でさらに説得力を持たせることに成功していたと思います。
特に、大人の更紗が海に入り叫ぶシーンや、文と子供の頃の更紗が見つめ合う正面のカットバックなど、ハッとさせられる映像がたくさんありました。
無理に照明を作りすぎず、自然光を大切にして部屋の中では陰影もしっかりと立たせている辺りが、撮影監督としての技量の高さを見せつけてくれたような気がしました。
(2)2人だけの真実。2人だけの愛
この物語の中で文は小児性愛者という一種の障害があるキャラクターとして登場します。けれど、自分はまともじゃないという感覚は文自身も感じていて、そのことによる葛藤も本作で描かれています。
冒頭で描かれる子供の更紗と大学生の文による出会い。家庭内で嫌がらせを受け続け、家で居場所がなかった更紗は、自らの意思で文の家に寝泊まりすることになります。
そこで描かれる二人の姿は年齢の枠を超えた、信頼し合う絆のようなものが生まれてくることに、観客は徐々に気付かされるのです。
冒頭の二人の楽しげな生活があってこそ、後半に起こる悲劇的な展開と救いの描写に心を動かされることになります。
二人が文の部屋の中で観ていた映画は、今敏監督の「パプリカ」でした。部屋には不自然にビー玉がたくさん転がり、子供の手作りのような仕切りがあり、「パプリカ」が流れている。
更紗と文が心を重ね合わせていく中で、とても重要で印象的な空間になっていると感じました。あの二人だけの神秘的な空間があったからこそ、更紗の心にはずっと文の存在がい続け、離れてくれないのではないかという現実味が帯びたのだと思います。
しかし、世間的には女児誘拐として更紗は捜索されることになります。ある時、更紗は、文に「私と一緒にいることで逮捕されてもいいの?」と問いかけます。その時の文の答は「困る。死んでも知られたくないことが世間にバレてしまうから」と返すのです。
このシーンで、普段感情を表に出さない文の本当の気持ちが、初めて表れたように思いました。
これまでの人生でひた隠しにしてきた「幼児しか愛せない」というマイノリティな障害を抱え、生きづらさを感じてきた文にとって、小児性愛者だと世間に知られることは死ぬほど嫌なことだったのです。
世間からの批判がさらに強まることになっても、恋人の亮との関係が終わりに向かっていっても、更紗は文への想いを止めることなく向き合っていきます。昔自分を救ってくれたように、今は文の幸せを願い、そして一緒にいたいと心から願う。そんな二人の普通じゃない愛の形に最後は応援する気持ちが溢れました。
二人にはずっと幸せでいて欲しい。この世界のどこかで笑顔で生きていてほしい。
そう願ってしまうほど、愛しく思えてくるのです。
(3)正解のない愛の形。答えのない善悪を描き続ける
李相日監督は、「悪人」そして「怒り」で答えのない善悪や真実に、真正面から向き合うテーマに挑み続けています。それがまるで、自分が映画を作り続ける意義であると宣言しているかのようです。本作でも根底に流れている「正解のない愛」「答えのない善悪」を世に問うために、6年の沈黙を破って映画を製作したのだと思いました。
大人と子供が恋をする。
この単純明快なことに犯罪のレッテルを掲げ、悪とみなすようになったのは一体いつからなのか。法律で定められているから悪なのか。
本人同士が絆で繋がっていてもそれは糾弾されるべきなのか。
大人の女性を愛することができない体は「ハズレ」なのか。
答えの出ないテーマを「流浪の月」を通して描きたかったのではないかと思いました。
そして李監督はもう一つ、重大なテーマを描いていたと感じています。
それは「メディアを通して流れるニュースは本当に真実か?報道のまま鵜呑みにして一元的に物事を見ることは正しいと言えるのか。物事はもっと多面的で当人たちしか知り得ない真実がそこにはあるのではないか」ということです。
物語の後半、更紗はバイト先の先輩から子供(リカ)を預かることになります。リカは更紗の部屋で一緒に数日間暮らすことになり、更紗の隣に住んでいた文も自然な流れでリカと遊ぶようになります。
世間から更紗との交流を暴露され、小児性愛者だということがバレた文には、女児といるだけで疑いの目を向けられてしまいます。
ある日、文が営む喫茶店で文とリカが一緒にいると、警察が突如現れ、文は無理矢理拘束されてしまいます。そして女性警察は、リカに向かって「もう大丈夫だよ」とあたかも文がリカに対して、無理矢理連れ去ったかのような言葉を投げかけます。
15年前、更紗の時にも行われた、他者からの介入で、前触れもなく崩れさる日常。リカを引き離される中で、文は「もうやめてくれ!」と神にもすがるような大声で絶叫するのです。
そのシーンを観て、自然と悔しくて涙が溢れました。
更紗が女児誘拐として処理された時と、また同じことが繰り返されている。更紗が望んだ文の「普通の生活」は、またしてもあっという間に壊され無くなってしまうのです。
このシーンから見えてくる、報道で流れる事件は、何が本当で何がフェイクか。そこを見極めるのは、結局のところ自分しかいないのです。
文は最後に母親との記憶を思い出します。母は文のことを異物として恐れるような目で見ており、気味悪そうにしていました。
実家の庭にある、養分が十分にいかず「ハズレ」として扱われた木がありました。母は文の目の前でその木を引っこ抜き、処分します。
大人の女性を愛せない体で生まれてしまった文は、そのハズレの木と自分を重ね合わせて自分はハズレなのか、自分は病気なのか、分からなくなる。
小児性愛者というだけで、社会から遠ざけられて排斥されてしまう。
そんな世の中は本当に正義なのか、そんなことを観賞後も考えてしまう心に残る一作でした。
まとめ
この映画に絶望はたくさんありますが、最後に訪れるのは更紗と文に向けた「救い」でした。
様々な困難を乗り越え、二人が到達した互いに向けた優しい眼差し。
その優しい眼差しに心を奪われ、ずっとずっと見ていたい。そう心から思わせられました。
本当に好きな邦画がまたできました。
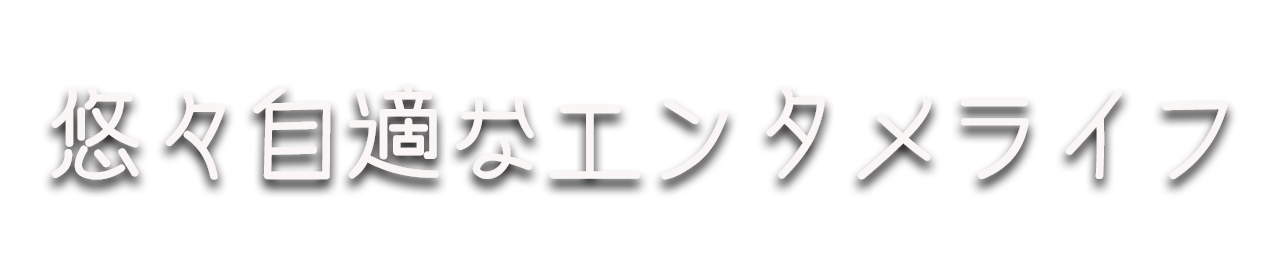



コメント